- ホーム
- いわさ はるみ|看護職のキャリアを考える
- ブログ
- 訪問看護ステーションで働く看護職を応援したい!!
訪問看護ステーションで働く看護職を応援したい!!
- 2025/07/01
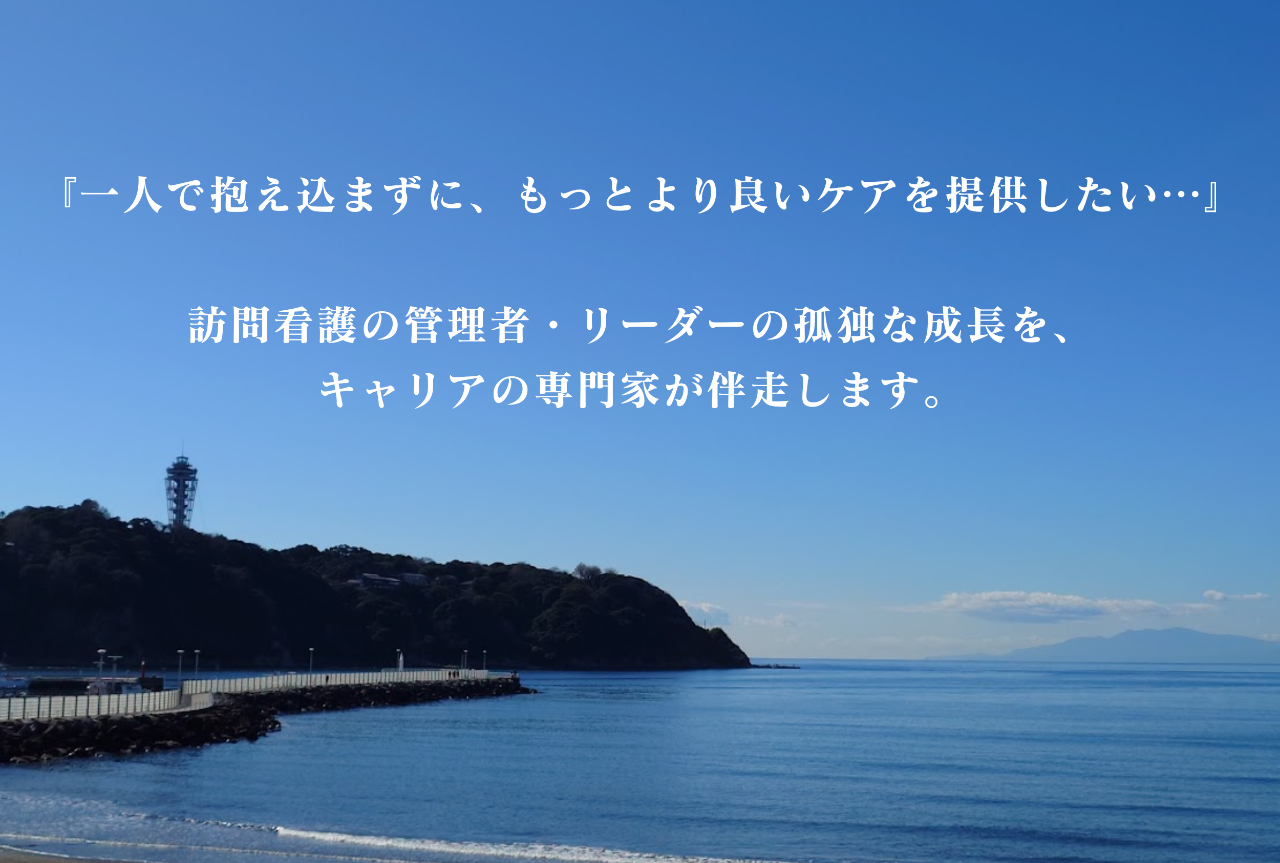
~なぜ訪問看護ステーションで働く看護職の支援をしようと思ったのか~看護職対象の相談支援を行っている「いわさ はるみ」と申します。神奈川県鎌倉市を拠点に活動しています。私は、看護師・保健師資格を持ち、これまで総合病院、保健指導の委託業務、子育て支援のNPO(茶話会の開催やベビーシッター等)を経験しながら、現在は看護職へメンターシップを提供したり、個人でキャリアカウンセリングを提供したりしています。
こんな私が、なぜ訪問看護ステーションで働く看護職への支援に力を入れていこうと考えたのか、それをまとめて記したのが今回のブログになります。
(1)管理職としてのジレンマ
看護師免許取得後、保健師免許を取得し、22歳で300床の病院に就職し、約16年間勤務しました。この16年間の勤務は、私にとって大変貴重な経験になりました。特に、そのうち10年間は管理業務に携わり、最後の2年間は病棟の立ち上げと病棟管理者としての役割を担いました。日々の診療報酬との闘いと、目の前の患者さん、スタッフへの配慮と、経営層から課せられる課題…毎日が楽しくも、厳しく、充実した日々だったと振り返ります。その中で私は、管理者が、病棟所属スタッフのメンタル支援を含む多岐にわたる支援を、管理業務と並行して行うことには限界があると痛感しました。スタッフの相談に乗る際、管理職という立場が邪魔をして、カウンセラーとして深く関われないもどかしさも感じました。加えて、管理者自身が安心して相談できる場が少ないことにも、課題意識を持ちました。
(2)外部支援って、必要じゃね!?
これらの経験から、外部支援者の必要性を強く感じるようになりました。利害関係のない第三者が、管理者である自分や、スタッフの日々のモヤモヤや困ったことを聞いてくれ、整理してくれるような介入をしてくれたら、もっと患者さんに集中できるのに…と思っていました。メンタル支援は、そこまで困難は感じなかったのですが、特にリワークプログラムなどは、制度も十分確立しておらず、なんだか手探り状態になってしまい、当時の当事者には、十分対応できたのかな…と、今でも時々振り返っています。医療の世界は、どこかで、自分の健康は自分で守れて当然よね的風潮があるように感じ、働く労働者の労働安全衛生(感染等は別として)への視点は、あまり重視されていないのかな…等考えていました。キャリア支援という観点では、院内の看護職のキャリア開発部門に所属し、管理・運営を行ってきました。その中で、大病院に比べて中小規模の職場は、支援に使えるリソースが少ないと感じていました。
時は流れ、色々あり(引っ越し・出産・育児等々…)、現場を離れて、私は考えたのです。あの当時必要だと思っていた外部資源に、自分がなればよいのではないかと。そして、私自身がキャリアコンサルタント等の資格を取得するに至り、現在は看護職を対象としたメンターシップを提供するプラットフォームに所属したり、個人で看護職専門にキャリアカウンセリングを提供したりしています。
(3)訪問看護は私の“あこがれ”
「あこがれるのをやめましょう」と大谷選手が語ったようですが、私が超える対象ではないので、今でもあこがれています。今回、訪問看護ステーションを対象とした一番の理由は、訪問看護師という仕事が長年の私の“あこがれ”だからです。学生の頃から、看護師より保健師の方が、自分に合っているかもな…と感じていて、行く行くは地域に出ていきたいと考えていました。看護師5年目の時に、訪問看護師になろうと一旦決意しました。すると、当時の看護部長に相談したところ、在宅移行支援の比重が大きい、回復期リハビリテーション病棟への配属を提案されました。結果的に11年間勤務しました。当時は、これから病棟を立ち上げるという局面で、なんだか面白そうと思ってしまい、そのまま主任職として移動しました。部長の思惑(?)に乗ってしまいましたが、このフィールドは大変楽しく、見抜かれていたのかなと、当時を振り返ります。
回復期リハビリテーション病棟では、地域に患者さんをつなげていくという視点が重要になります。そのため、患者さんを“生活者”として見ていました。また、医師も急性期病棟ほど来棟しない状況があるので、こちらから症状の報告をし、併せて提案をするという能力が求められます。急性期が医師の治療を重視して動くのと比較すると、回復期では看護師が疾患と生活を見極めて、全体のマネジメントしていくウエイトが非常に大きいかったと振り返ります。部署柄、家屋調査のために外に出たり、訪問看護師さんや、ケアマネージャーさん、ヘルパーさん等と接する機会が多く、在宅看護を意識しつつ、病院という場で看護できていたのは、自分に合っていたのだろうと思います。そして、訪問看護師さんと、少し求められる機能が似ているなとも思っていました。
また、在宅成分(?)を更に得るために、院内の在宅移行に関する委員会の管理者や、訪問看護に関する院内研修の計画実施等、積極的に在宅看護分野に関わってきました。
(4)訪問看護が注目されている現代
地域包括ケアシステムの推進や高齢化を背景に、私が居住している神奈川県内の訪問看護ステーション数は、2010年の322事業所から2023年には942事業所へと、約13年間で約3倍に増加しています。しかし、その一方で、10人未満の小規模な訪問看護ステーションが全体の約7割を占めているのが現状です。
病院勤務の看護師が訪問看護ステーションへ転職するケースが増える中、新たな環境への円滑な移行には「学び直し」が不可欠です。しかし、小規模なステーションでは、こうした移行支援や教育に充てるリソースが不足しているのではないかと懸念しています。実際に、離職率の高さや、離職理由に教育体制やキャリアパスへの不満、人間関係等の現状が見られます。
加えて、特に管理者は、現場の運営、人事、経理、そしてプレイヤーとしての業務を兼務し、多忙な中で孤軍奮闘しているのが現状ではないでしょうか。
(5)もやもや、お困りごとを相談できる、駆け込み寺をつくる
訪問看護師のみなさんが、「困ったこと」や「モヤモヤ」を気軽に相談でき、前向きに業務に取り組めるようになることで、スタッフと利用者双方に良い影響がもたらされると考えます。そして、それは、同じ看護というライセンスを持って、この時代を一緒に生きてきた自分だからこそ、共感できることが多いのではないかなと思います。こころの中にあるモヤモヤを、言葉にし、整理することで、次のステップを探すお手伝いをさせてください。ひとりひとりの変化と行動が、波紋となり、職場のスタッフや利用者さん、これから訪問看護に出会う人達にまで届いていく姿を想像しています。
